「へぇ?」
そんな、言葉とも言えないような音を発して、ミサトさんは少し呆気に取られたような
表情を浮かべた。突然何を言いだすのだろう、この子は? そんな心の声が聞こえてきそ
うな目で、すぐ隣のシートに座るボクのことをジっと見つめる。
でも、その視線を受けとめる形となったボクにとっても、その言葉は自分自身を戸惑わ
せるのに十分なものだった。実際、言ってしまった後で、当の自分が少し驚いていた。な
んでこんなこと言ってるんだろうボクは、って。
「あの、信号、青ですよ」
少し居心地の悪い静寂を破るその言葉に、ミサトさんの視線がボクから慌てて外され、
ほぼ同時に左手と両足が忙しく動かされる。手馴れた様子で一連の動作を流麗にこなすと、
エンジンの動力がタイヤに伝えられ、軽いホイルスピンを起こして車が動き出した。
横目でミサトさんの様子を盗み見る。黒いスカート、ベージュ色のVネックシャツ、そ
の上に羽織られた赤いジャケット、肩より少し伸ばされた髪。その視線は前方に固定され
たまま、ボクの方に向けられる気配はなかった。
(やっぱり、聞かなきゃよかったかな……)
軽い後悔で心が少しずつ満たされていく。何を考えているのかと、からかわれるかもし
れない。変な奴だと思われたのかもしれない。ずうずうしい奴だと、内心面白くないのか
もしれない。そんな自分の中からこみ上げてくる不安に、ボクはどうしようもなく視線を
落とす。
振り返ってみれば、この話題を切り出すまでミサトさんはいつも以上におしゃべりだっ
た。
『今度の土曜日は久しぶりの休暇が取れたの。もう日曜の今から楽しみでさぁ。何をしよ
うかいろいろ考えてるんだけど、不思議なのよね、いざ時間があるとなると、案外やりた
いことを思いつかないの。考えてみたら、こっちでは一緒につるむ相手もリツコ以外には
いないんだけど、あいつ最近付き合い悪いしさ。だから昼までは家でゆっくりと寝て、午
後はどこかにショッピングなんてことになるかなあ、なんて思うのよね。んで、帰ったら
シンちゃんの美味しい料理にビールの一杯でもありゃあ幸せだわね〜』
そんなことを一気に言ってしまった後、まるで自分のささやかな幸せをお裾分けするか
のような笑顔と共に、ミサトさんは次の土曜のボクの予定を尋ねてきたのだった。
でも、そう聞かれたところで、ボクにすることなんてなかった。土曜日といえば、横須
賀に何とかという軍艦が入ってくる日だと散々聞かされていたから、きっとケンスケはそ
っちのほうに行ってしまうだろうし、トウジはいつも通り妹のお見舞いのはず。だから、
つるむ相手がいないのは自分も同じだ、ということを答える。
『あら、だったらレイをデートにでも誘えばいいじゃないのよ〜』
するとミサトさんは、背筋を震わす邪悪な笑みと共に、そんなことを突然切り出してき
たのだった。
ヤシマ作戦以来ミサトさんはずっとそんな調子で、それはボクのちょっとした悩みにな
りつつあった。あのとき綾波の前で涙を流しているところを見られて以来、何かといえば
ミサトさんはそういった方向に話を飛躍させようとしていたからだ。
『そ、そんなことするわけないじゃないですか!』
そんな他愛のないからかいをサラリと流せる……ほどにボクは大人ではない。だから、
ついつい声を張り上げて、そんなことを主張してしまうのだけど、今回はそれが益々火に
油を注ぐことになってしまった。裏返ってしまった声と、言葉の頭の少しのどもり。当然
というか、ミサトさんがそんなチャンスを見逃すはずもなく、更に壮絶なものになった笑
みと共に、その後もしばらく集中攻撃は続いた。
(ミサトさんって基本的にいい人だけど、ああいうところは勘弁してほしいな……)
第二使徒戦で使ったパレットライフルもかくやという調子で、次々とその口から飛び出
してくる冷やかしの言葉がどうにか一段落し、台風が通りすぎた後のような静けさがよう
やく戻ってくる。でも横目でチラリと見たミサトさんにはまだあの笑みが浮かんでいたか
ら、ボクはどうにか話題を変えてそれ以上の追求をかわそうと、焦りながらも、思いつい
たことをほとんど無意識に口にした。そうしたらミサトさんは急に黙り込んでしまい、そ
の状況が今も続いている。
さして広くもない空間を満たす沈黙に、なんだか居たたまれない思いだった。
(黙ったまま、うやむやにされちゃうのかな? 答える必要ないって……。そうだよな、
ひょっとしたら、ミサトさんの方にも何か事情があるのかもしれないんだから……)
そうして何もなかったように家に帰り、夕食を取って、いつものようにビールを飲むの
だろうか。もし、そうなら、それはそれでいいかもしれない。そんな思いが湧き上がって
くる。
(もしボクがミサトさんの気に障ることを聞いたのなら、何も言わずに忘れた方がお互い
のためだもんな……)
そう、嫌なことは忘れてしまえばいい。そして何もなかったかのように、また普段の生
活に戻っていけばいい。ミサトさんと同居しているボクにとって、二人の間の亀裂になり
かねないことを自分の手で作り出す理由なんてどこにもない。だからこのことに関しては
これで終わりにしたほうがいい。そんな考え方で、ボクは自分自身を納得させることにし
た。
そのままお互い言葉を発しない状態が続き、外の光景と時間だけが緩やかに流れていく。
特に何をするというわけでもなく、ただボーっとガラス越しの風景を眺めていると、少し
体が前に引っ張られる感覚と共に、車が減速を始めた。
赤信号で一時停車をするボクたちの目の前を、仲睦ましい様子で横断歩道を渡る親子の
姿が横切っていく。優しそうな微笑みを浮かべたお母さんは左手で小さな女の子の手を握
り、空いた方の腕にはどこかのスーパーのものと思しき買い物袋がぶら下げられていた。
(そうだ、そういえば、今日はどうしよう)
そんな光景にボクがその日の夕食の献立を考え始めた時、何の前触れもなく沈黙が破ら
れた。
「そう……ね。なんて言ったらいいのかな。どう……接したらいいのか分からなかったの
よ。……私の言いたいこと、何となく分かるでしょ?」
一瞬思考に空白が生まれ、すぐに、ああ、さっきのことを話しているのだと思い当たっ
た。自分の心の深くて暗い所に沈めかけた記憶を慌ててサルベージし、ミサトさんの言う
ことと自分の言ったことの辻褄を合わせる。
「あ、はい……。分かる気がします」
そう。あの子にはどういう対応をしたらいいのか、それはボクにとっても大きな問題だ
った。実際この間のヤシマ作戦まで、自分はあの子、綾波レイ、に嫌われているんだと思
っていたから。それだけのことはしていると思っていたし、女の子に思いっきり引っ叩か
れるというボクにとっては衝撃的な事件もあったことだし……。だからあの子が自分とマ
トモに口をきいてくれなくてもしょうがない。そう思っていた。
ただ、ビンタに関してはともかく、聞いてみると、綾波という子は誰に対してもああい
った態度を取るらしい。会話しようとして何かを聞いても、必要以上のことは絶対に答え
ないし、自分からも必要以上のことは言わない。それにどこか人を寄せ付けない独特の雰
囲気が彼女にはある。一体あの子にはどんな風に向き合ったらいいのだろう、とはボクだ
けの思いではないらしい。
(でも、ミサトさんみたいに人当たりのいい人でもやっぱりそうなのかな?)
そんな疑問を何気なく口にすると、ミサトさんは一瞬複雑な笑みを浮かべた。その口元
は確かに微笑んでいるように見えたけれど、黒い瞳の奥に湛えられた光からは、どこか寂
しげで沈むような印象を受ける。
(ミサトさんのこんな表情、始めてだ……)
そんな風に思ったけれど、それについて深く考える時間をミサトさんは与えてくれなか
った。ふと気がつくと、いつのまにかその顔からは暗い雰囲気が消えていて、何かを楽し
むような満面の笑みがそれに取って代わっている。
「そんなことよりも、何よ、突然そんな話しちゃってさ。やっぱりレイのことが気になる
んだ〜? 嫌ねえ、シンちゃんたら。そうならそうと言ってくれればいいのに」
「……」
その言葉に内心で深い溜息をつく。ミサトさんは、本当に他人を冷やかすチャンスは絶
対逃さない。性格的に、火のないところでも無理矢理に煙を立てちゃうタイプってやつ。
これって結構真面目な話題だと思うのに、どうしてそっちの方向に引っ張っていっちゃう
んだろう。
「べ、別にそういうんじゃないです……。ボクは……ただ……あんな人気のないところで
一人っきりで過ごすのって、きっと寂しいだろうなって……。それって、なんだか可哀想
だなって思って……。どうして、みんな放っておくんだろうって思って……」
初めてあの部屋に行ったときのことは忘れられなかった。いい意味ではなく、悪い意味
でとても強烈な印象があったから。すぐ後の「事故」のせいでバタバタしてしまったけれ
ど、冷静に考えると、あの部屋はどうみても異常だ。綾波には悪いけれど、まともな人間
の住むところじゃないと思う。だって、あまりに寂しすぎるんだ。生きてるって感じが全
くしない、あの部屋は。
『私には、他に何もないもの』
もしその言葉が本当なら、綾波はあの部屋で、エヴァに乗るというただその目的のため
だけに、たった一人で寂しく毎日を生きているのだろうか? そう思うとキュっと胸が痛
んだ。
だからといって、具体的にどうこうしたいとか、そういうことまでに考えが及んだわけ
じゃない。例えば、少しでも綾波の孤独を癒してあげたいとか、そういったことは冗談で
も思えなかった。なぜって、自分のことだけでも精一杯なボクなんかが、他人に与えてあ
げられるものを持っているはずがないし、何より、綾波がそんなことをしてほしいと思っ
ているわけもない。
ただ、そんな中でも一つだけハッキリと思ったことがある。
(でも、綾波も何かエヴァ以外に大事に思えるものを見つけられたらいいのにな……)
何で、そんなことを考えたのかよく分からない。
ただ、何となく綾波には同じ匂いを感じた。
少しボクみたいだと思った。
あの子の儚い瞳と凛とした強さに、胸の中が不思議な感覚で満たされていった。
もっとあの子のことが知りたいと思った。
重傷を負いながらも、必死にエヴァに乗ろうとする彼女を動かすものは何なんだろう?
『私には他に何もないもの』あの子にそう言わせるものってなんだろう?
何故あの子はいつも無表情なんだろう?
あの子は父さんの何なんだろう?
あの子は一人で寂しくないのだろうか?
ヤシマ作戦の前には、きっとこんな気持ちにはならなかった。でも、降り注ぐ淡い月光
の下で、短いながらも確かに会話を交わしたこと。そこで少しだけ、綾波レイという謎め
いた子の内面を見た気がしたこと。裸を見られても表情一つ変えなかった彼女が微笑んで
くれたこと。そうした事実がボクの心を少しだけ変えたのだと思う。
そうなんだ。あの子だって苦痛に顔を歪めるし、父さんに対してそうしたように表情だ
って和らげるし、ボクにしたように人の頬を叩くし、それに、笑うんだ。そう、綾波の笑
顔は、なんというか、素敵だった。また見たいなと思う。また微笑んでくれたらいいなと
思う。普段無愛想なところがあるから尚更なんだ。だから一瞬見惚れてしまったんだ……。
(……でも、不思議だな。何で綾波のことがこんなに気になるんだろう)
本当は、そんな理屈なんてどうでもいいことなのかもしれない。確かなのは、ボクの心
の片隅に、綾波レイを住人とする小さな場所ができたということだった。
「じゃあさ、レイに聞いてみようか。私のところに来ないって」
物思いに耽りすぎたのか、突然かけられた声にボクの体がピクリと震える。
(え、今なんて?)
一瞬の混乱の後、記号だったミサトさんの言葉が、意味となってボクの頭に染み込んで
くる。それに比例して段々自分がうろたえていくのが、まるで他人事のようにハッキリと
分かった。あまりに突然で飛躍しすぎたその言葉に、何故だか少し顔が赤くなるのが自分
でも感じ取れる。
「い、いや、ボクはそんな意味で言ったわけじゃあ。それに、それはまずいですよ」
「あら、どうして? シンちゃんはレイのことが嫌いなの?」
「や、嫌いとかそういう問題じゃないですよ。何でいきなりそうなるんですか」
「んん〜? シンちゃんったら、何をうろたえてるのかなぁ?」
ミサトさんに再びあのニタニタ笑いが浮かんだ。ああ、またくるな、と感じたボクは、
最大戦速で頭を働かせ、心中密かに防衛手段を考え始める。
でも、いくら待ってもボクが予想しているような言葉は飛んでこなかった。逆にミサト
さんの表情はいつのまにかフッと真面目なものになり、その声は、ミサトさん、というよ
りは葛城一尉のそれに変化していた。
「まあそんな冗談はともかく……。レイをあそこに置いておくのはよくないっていうのは、
私自身も思っていたことなの。あの子のあまりにも世間知らずなところとか、人との付き
合い方を知らない様子を見ているとね……。決して無視していたわけじゃないのよ。ただ
ね……シンジ君が来る前は自信がなかったの。自分はあの子と二人だけでやっていけるの
かな、ってね……」
「……分かる……気がします」
「さっきシンジ君は、私のことを人当たりがいいと言ったわよね。……けど、ホントはそ
うでもないのよ。どちらかといえば苦手なのよね。他人との一対一って……」
快活で、冗談好きで、とても真っ直ぐな人。それがボクの持つミサトさんの印象だった。
だから、それとはあまりに違う事実を告げる言葉に、ボクは思わずその顔を見つめてしま
った。どこか遠いところを見るような目をしていたミサトさんは、その視線に気がつくと
すぐに表情を緩め、不自然なくらいに明るい声を張り上げる。
「ま、今はシンちゃんも家にいるわけだしね。状況も全然違うもんね……」
「……?」
「ね、シンジ君。もし私が、レイを家に引き取ろうかと思う、って言ったら、シンジ君は
どう?」
(どうって言われても……)
ボクに反対する理由なんかなかった。だから、そう言った。ずるい言い方だと思う。
反対する理由がない? それは賛成なのか? ボクの意志を聞いているんじゃないか。
「そ、それにあそこはミサトさんの部屋ですから、ボクがどうこう言うことじゃ……」
そんなことを言った後で自己嫌悪になる。
そういう言い方しかできない、他人に何かを押しつけて逃げているだけの自分。それは
確かに楽なこと。だって、いざというときに他人のせいにできるんだから。でもボクはそ
んな自分が嫌いだったし、少しずつでも変わっていきたいと思っていた。けれどそんな思
いとは裏腹に、こういうときにそれが容赦なく暴かれてしまう。結局自分は何も変わって
いないんだということが……。
「あら、でもこれって大事なことだもの。家族の一員に相談するのは当然でしょ?」
ミサトさんにその気はないのだろうけれど、追い討ちをかけるようなその言葉に自分が
益々嫌になってしまった。
(初めてあの部屋に行ったときから、ミサトさんはずっとボクのことを家族として見よう
としてくれている。なのに、自分はどうしてああいうバカなことしか言えないんだろう。
ミサトさんはボクたちの間の壁を取り除こうと努力してくれているのに、結局ボクの方に
はまだ心許していない部分、負い目を感じているところがあるってことなんだ……)
そんな反面、家族の一員と言ってもらえたこと、大事だと思っていることに関してミサ
トさんに相談してもらえたという事実は、心の中の深い泥沼に沈み込みそうになるボクに
差し伸べられた、温かい救いの手のように感じられた。
そんなミサトさんの心遣いに答えなければという思いもあったし、自分の中にモヤモヤ
したものを残したくないというのもある。そして、底の見えない暗くて深い思考の海の中
には、自分でもどう触れていいのか分からない不思議な想いが、確かにユラユラと漂い続
けていた。そうした感情が複雑に絡み合う中、ボクは膝の上で軽く拳を握り、何度か瞬き
を繰り返した後、なけなしの勇気を振るい出してどうにか口を開いた。
「……あ、あの、ボクも……いい……と思います。綾波が、その、家に、来るのは……」
その言葉を耳にしたミサトさんは、ボクを一瞥し、何も答えずにただ微笑むと、軽快な
仕草でシフトレバーを操作し更に1速ギアを上げた。エンジンがその気持ちを代弁するか
のように甲高い咆哮をあげ、回転数と共に周りの景色の流れるスピードが上がっていく。
少しだけ前に進めたというささやかな達成感。
少しだけ心が通じたかもしれないという温かな気持ち。
あの子にも同じ気持ちを感じることができるだろうか。
あの子、綾波とも家族になれるだろうか……。
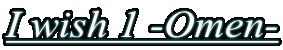
少女にとって、それは何の変哲もない一日のはずだった。朝目覚め、シャワーを浴び、
学校へ向かう支度をする。殺風景な部屋の中には、時を告げる類のものは全く見当たらな
いが、毎朝計ったかのように同じ時間に家を出て、数分ほど歩いた場所でいつもと同じ時
刻のバスに乗る。通勤通学時にも関わらず、さして人の多くない車内で15分ほど本を読
んで時間を過ごした後、いつものバス停で降り、4、5分ほど離れた学校まで少し歩く。
それが、綾波レイにとってのその日の始まりだった。
週末のスタートを翌日に控えたその日、レイの日常生活において重要な位置を占めるエ
ヴァンゲリオンのテストの予定は組まれていない。それゆえ、学校に登校し授業終了まで
そこで時間を過ごす予定だった。特に問題は、ない。2ヶ月ほど前にやってきた新しいク
ラスメート、そして同僚でもある初号機パイロットが自分の方をチラチラ伺っているのに
気付いたが、目が合うと、向こうは慌てたように視線を外してしまう。そんな様子に微か
なひっかかりを感じつつも、何か用件があるならば彼の方からいずれ話してくるだろうと、
レイは手にしていた文庫本に再び目を落とすのだった。
ただの365分の1であるはずのその一日が少しずつ動き出したのは、昼休みのこと。
緊急時の呼び出しがあった時のために、学校でもメロディ使用にしてある携帯電話が突然
無機質な音を響かせ始めたのだ。
使徒が襲来したときのための緊急呼び出し用のそれとは違う音楽。だからレイは少しも
慌てることなく、音の発信源を取り出した。スクリーンに視線を滑らせ、発信者を確認す
るまでもない。緊急時以外で彼女に電話をするのはあの人物以外には一人としていないの
だから。
『レイ、私よ。今日はちょっと用件があるから、5時に私の部屋まで来ること。いいわね』
了解の旨を伝えると、時間通りに来るのよ、という言葉を残し、回線が向こうから切断
された。周りで昼食を取るクラスメートがその会話を聞くことができたなら、あまりにも
素っ気無さすぎる通話相手の口調に多少の戸惑いと不信の念を感じたかもしれないが、レ
イにとっては、それもまた日常の一コマに過ぎなかった。用件を簡潔に相手に伝えること。
それが最も重要なこと。赤木リツコとは、世間話をすることが目的ではないのだから。
授業終了後に掃除を済ませ、本部直通のリニアの駅に向かう。レイには突然呼び出され
る理由がわからなかった。週に一度の定期検診は二日前に済ませてある。何か特別な用件
があるのだろうか。エヴァのテストに関する通達事項だろうか。他にも考えられる可能性
をいろいろと思い浮かべてみたが、どれも決定的な確信へと進化するには至らなかった。
(…よく、分からない)
でも、考えてもしょうがないことだ、とレイは気持ちを切り替えることにした。何か用
があるから呼ばれるのだし、行ってみれば、それが何なのかはわかるはず。自分があれこ
れと思いを巡らせることには何の意味もない。ただ命令されたことを自分はこなしていけ
ばいい。いままでずっとそうだったのだから。
いつもと同じリフトを使い、
いつもと同じ廊下を通り、
いつもと同じドアの前に立ち、
いつもと同じように呼び出しベルを鳴らし、
いつもと同じ光景の部屋に入ると、
いつもと同じ白衣を着たリツコに椅子を勧められた。
いつもはそんなことはないのに。
「あなたは今のところに住み始めてどのくらいになるかしら?」
そんな問いかけから会話が始まる。感じるのは若干の違和感。赤木リツコは、先程の電
話での会話がそうだったように、いつも要点を簡潔に述べる人物だった。そして必要のあ
る場合には、その後でそれを補足する説明をする。少なくともレイにはいつもそうした態
度で臨んできた。
では、何故今日は回りくどい言い方をするのだろう。それに、問いかけの答えをリツコ
は知っているはず。何故意味のない問いをするのだろう。そんな思いに加えて、リツコの
雰囲気がいつもとは少し違うことをレイは感じ取っていた。
(…少し、穏やかな感じ)
いつも顔を合わせるときのピンと張り詰めた緊張感はそこにはなく、まるで会話を楽し
もうとするようなリラックスした空気が、微かな微笑みを浮かべるリツコからは発せられ
ていた。そうした部分まで読み取ることはレイの未発達な心にはいささか荷の重いことだ
ったが、リツコから受ける印象がいつもとはどこか違うということはハッキリと認識する。
(…でも、関係ない)
しかし、それはレイにとって重要なことではない。今自分がすべきことは問われたこと
に答えること。質問者の様子を伺うことではない。だから、答える。
「…一年半ほどです」
「そうね。今の所は気にいっている?」
まるでその答えを待っていたかのように、間髪入れず再度問いが発せられる。
(…気にいっている? よく、分からない)
それまで、そうしたことは考えたこともなかったし、そうする必要があるとも思えなか
った。雨をしのぎ、休息を取り、生活に不可欠なことをする場所。それがレイにとっての
住居。気に入っているかどうかは問題ではない。だからそう答えると、リツコはフッと微
笑を浮かべた。
「実はね、あなたに同居を申し出ている人がいるのよ」
意味がよく把握できないその質問に、レイは多少の戸惑いを感じた。
(…同居。一緒に住むということ)
その脳裏に、一瞬あるイメージが形どられる。その人物は、少女の属する組織の最高司
令官であり、綾波レイという存在自体を作り出した人物であり、その運命の支配者でもあ
る。その関係をどういう形で表現するにせよ、他人との繋がりが極端に薄いレイにとって、
同居などという行動を取りそうな人物で、他に思い当たるところはない。
(…でも、そんなはずない)
しかし、それもまた厳然たる事実だった。その意志があるのなら、ずっと昔にそうなっ
ていた筈だし、今になって突然そんなことをする理由はない。それが分かりすぎるくらい
に分かっていた。だから、戸惑っている。あの人意外に一体誰がそんなことを、と。
「誰だと思う?」
そんなレイの内心の揺らぎを見透かしたかのように、リツコがけしかけるような問いを
投げかける。
(…誰? 分からない。いくら考えても、きっと同じ)
きっとこの人は問いかけの答えを知っている。それなら早く教えてくれればいいのに。
そんなことをレイは感じた。目の前で何か大事そうなものをちらつかせ、明らかに相手の
様子の観察を楽しんでいるリツコに、焦らされていると思ったからではない。単純に、こ
ういった無駄な時間を過ごすことには何の意味もない、用件は手早く済ませた方がお互い
のためなのに、と思ったからだ。
「…分かりません」
「あら、そう?」
その声に微かに含まれる失望の響きは、葛城ミサトのように付き合いの長い人物でも感
じ取ることができたろうか、という程度のものだった。だからそれに気付くはずもないレ
イに出来るのは、ただそこに佇みリツコの口から次の言葉が発されるのを待つくらいのこ
とである。
「正解は……碇シンジ君」
「……」
やや勿体がつけられたそのセリフに、それまで俯かせていた顔と視線を僅かに上げ、レ
イはリツコのことを少しの間見つめた。交錯する視線。リツコはレイの様子を数秒間伺う
と、何かに満足したかのように少し微笑んだ。
「シンジ君がミサト……葛城一尉と一緒に住んでいるのは知っているわね?」
頷く。その事実は知っていた。
「そのシンジ君が、あなたと同居したいと葛城一尉に言ったらしいのよ」
再び俯くレイ。
(…今日は、分からないことが多い)
何故だろう。そうする理由など何もないはずなのに、どうして彼は自分と同居したいと
いうのだろう。碇司令からそうしろという命令を受けたのだろうか。赤木博士はそれにつ
いて何かを知っているのだろうか。そんな疑問を言葉に乗せて問いかける。
「…何故ですか?」
その問いに軽く肩をすくめるリツコ。その顔にはまだ微かな微笑が浮かんでいる。
「さあ。一目ボレでもされたのかしらね、あなた」
「………?」
一目ボレ。一目で恋に落ちるということ。そうした現象があるという知識は、以前読ん
だ本から学んでいた。レイにとっては、全くもって不可解で理解できないことだらけの本
だったが、不思議とそれについて語られた部分は印象に残っていた。だが、今重要なのは
そんなことではない。
(…どうして?)
結局全ての思考はその一点に向けて収縮する。どこか考え込む様子のレイからは、しば
らく言葉が発される気配は認められなかった。
一方で、そんなレイの様子を明らかに楽しんでいるリツコは、意図してのことかそうで
ないのか、益々レイを混乱させることを語りだす。
「シンジ君には以前からあなたのことを気にする素振りがあったし、ヤシマ作戦の様子を
見る限りでは、あながちその可能性も否定できないんじゃないかしら?」
探るような視線と、駆け引きを楽しむかのような微笑と共に、リツコは更に続ける。
「もしそんなに気になるなら、シンジ君に直接聞いてみることね」
「……」
その言葉にも、相変わらずレイは俯き、出口の見えない思考の迷路を彷徨っているよう
に見えた。他人とのコミュニケーションの中で目の前の少女が主導権を握ることはほとん
どない。それをよく知るリツコは、レイの様子に構わず話を続けた。
「それで、レイ。どうするの?」
「…何がですか?」
リツコの顔に再び浮かぶ笑みに、今日の赤木博士はよく笑うとレイは感じたが、今回の
微笑は先刻までのそれとはどこか質を異にしているように思えた。その口からは、あの子
も苦労しそうね、などという呟きが聞こえてくる。
「同居の申し出に応じるのかどうかって聞いているの」
「……」
レイにしてみれば特に断るべき理由はない。現在住んでいる部屋に愛着があるわけでは
ないし、セキュリティや緊急時の行動を考えれば、むしろシンジやミサトと近い所にいた
ほうが何かと好都合だろう。だとすれば、二人と同じ部屋に住むことは、しごく理性的な
ことかもしれない。
(…彼も、そう思ったの?)
だから、同居を申し出たというのなら、それは筋が通る話に思えた。
「…問題ありません」
「そう。むこうの受け入れ態勢は既に万全のようよ。あなたは私物もさほど多くないはず
だから、早速葛城一尉のところに移ってしまったらどう? シンジ君が食堂の前であなた
を迎えに来ているはずだから、声をかけていきなさい」
「…了解しました」
「用件は以上よ」
それは会話の終了の宣言でもあり、遠まわしに部屋からの退出を促すシグナルでもあっ
た。そのことを感じられるほどには、レイはリツコのことを理解していたから、素直に部
屋の出口へと向かう。
すると、ドアを開き部屋を出ようという間際に、突然背後から声をかけられた。
「シンジ君とうまくやるのよ」
それは命令だろうかと一瞬レイは迷ったが、その口調から判断すれば、きっとそれに準
ずるものなのだろうと判断した。だとするなら、自分はそれに従わなければならない。
と、そこまで思考を進めて、レイは、はたと立ち止まった。
(…どうすれば、いいの?)
今までも様々な形での命令を受けてきたが、しかし、そこにはいつも的確な指示が一緒
だった。自分がすべきことに関しては細かい説明があり、ある意味では、それを正確にト
レースすることこそが与えられた任務だったといえるかもしれない。
それゆえ今回も、どうすれば彼とうまくやれるのか、その方法を教えてほしいと思った
のも、レイにとっては自然なことであり、当然のごとく浮かんできた疑問だった。だから
それを尋ねた後で、少し間が空いてからリツコの顔に再び笑みが浮かび、数瞬の後には声
を押し殺すようにしてクスクス笑い出したのを見て、レイは何が起こっているのか理解す
ることができなかった。
(…何故、笑うの?)
自分が何か奇妙なことをしたのだという自覚はないし、こういうときにはどういった行
動を取ればいいのか、分からない。だからレイは、取りあえずリツコの笑いの発作がおさ
まるのを待つことにした。今日はいろいろ不思議なことが起こる日だ、などと他人事のよ
うな思いを持ちつつ。
10秒ほどそうしていただろうか。リツコは軽く目尻をぬぐうと、ようやくレイに視線
を向けた。
「さあね。とりあえず街に出かけて、一緒にお茶でも飲んでみたら?」
「……」
少女の持つ知識を総動員しても、やはりリツコの答えを理解することは出来なかった。
誰か他の者が聞いたなら、リツコのからかうような口調に、言葉の裏に隠された意図を感
じ取っただろうが、レイにそんなことを期待するのはいささか酷というもの。
「…了解しました」
だから、結局その口から出てきたのはそんな言葉だった。
「そう。まあ、頑張りなさいな」
そんなことを呟いた後で自分の机に向かってしまったリツコの背中をしばし見つめてか
ら、レイはその身を翻す。今日、赤木博士は何か機嫌がよくなることがあったに違いない。
そんな思いを胸に、レイはリツコの部屋を後にするのだった。
ぜひあなたの感想をSeven Sistersさんまでお送りください >[lineker_no_10@hotmail.com]
【投稿作品の目次】
【HOME】
【I wish contents】